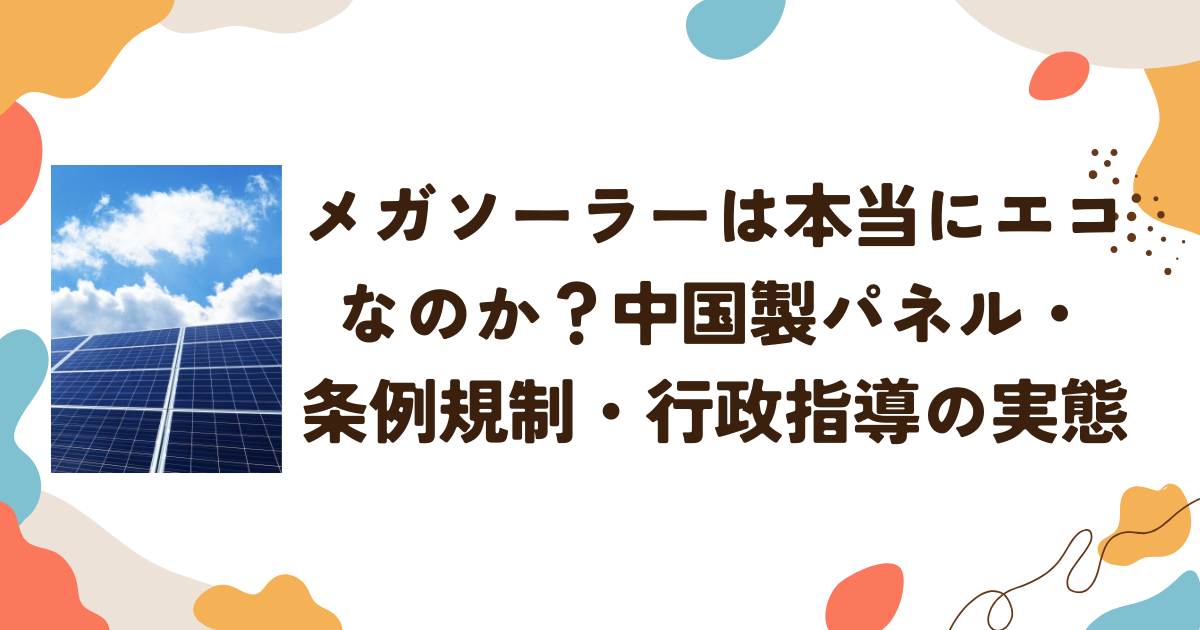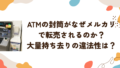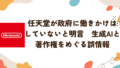日本各地で山林を切り開いて巨大な太陽光パネルを敷き詰める「メガソーラー」開発が進んでいます。一見すると環境に優しい再生可能エネルギーの取り組みに見えますが、実際の現場では「森林破壊」「土砂災害リスク」「所有者不明」「中国企業の関与」など、さまざまな問題が指摘されています。
千葉県鴨川市では、146ヘクタールの山林で36万本の樹木が伐採され、伐採木が谷底に放置されたままになっています。北海道・釧路でも釧路湿原周辺にメガソーラーが建設され、景観や自然保護の観点から大きな議論となっています。
この記事では、「メガソーラーとは何か?」という基本から、「なぜ中国企業が多いのか」「どれくらい発電できるのか」「なぜ問題になるのか」まで、事例を交えて分かりやすく解説します。
メガソーラーとは?どれくらいの規模から「メガ」なのか
メガソーラーとは、出力1メガワット(MW)以上の太陽光発電所のことを指します。1MWはおよそ一般家庭300世帯分の年間電力に相当します。千葉・鴨川のケースのように数十MW規模になると、数万世帯分の電力を賄える計算になります。
ただし、太陽光発電は天候によって発電量が大きく変動するため、火力・原子力などの電源を完全に代替することはできません。あくまで補助的な電源として捉えるのが現実的です。
なぜ中国企業が多いのか──日本のメガソーラーに中国資本が関与する理由
日本のメガソーラー事業には中国系企業が多数関与しているケースがあります。理由は以下の通りです。
- 太陽光パネルの世界シェアの8割以上が中国製であり、調達コストが安い
- 日本の固定価格買取制度(FIT)により、建設後の売電収入が保証されている
- 企業の所在地が実体のない事務所や名義貸しの場合もあり、責任所在が曖昧になりやすい
鴨川市の事業者も、オフィス内に家具がひとつもなく、会社名を手書きの紙で貼っていたと報じられています。こうした「実態の見えない事業者」が山を切り開いていることに、住民が不安を募らせるのは当然です。
メガソーラーの何が問題視されているのか
山林伐採による土砂災害リスク
樹木がなくなると雨水を蓄える力が失われ、一気に地表を流れ落ちて土砂崩れの危険が高まります。伐採木がその場に放置されていると、流木が障害物となり水害の被害をさらに拡大させる可能性があります。
メンテナンス・撤去費用が不透明
太陽光パネルの寿命は20〜30年とされていますが、撤去時の費用負担が明確になっていません。「発電して儲けた後は放置されるのではないか」という懸念が各地で広がっています。
景観・生態系・観光資源への影響
とくに観光地や自然保護区域では、「森や湿地がパネルの海になってしまう」といった批判が出ています。鳥獣の生息地が失われたり、河川が濁ったりするなど副作用も無視できません。
太陽光発電はどれくらい発電できるのか
太陽光発電の発電量は「施設の規模 × 日射量 × 稼働率」で決まります。日本の平均的な稼働率は約12〜15%と言われており、これは「昼間だけ発電し、曇りや雨の日はほとんど発電しない」という現実を反映しています。
- 1MW(メガワット)=年間およそ100万kWh前後の発電が見込まれます
- これは一般家庭約300〜350世帯分に相当します
たとえば鴨川市の計画が仮に100MW規模で稼働したとすれば、およそ3万世帯分の電力を供給できる計算になります。数字だけ見れば大きく感じられますが、天候による変動幅が激しいため、「安定供給できる電源」とは言えません。
さらに、冬季の積雪がある地域や、黄砂・火山灰などが降る地域ではパネルが汚れて発電効率が大きく下がります。メガソーラーは「常に全力で動いている電源」ではないという点を理解しておく必要があります。
中国で再エネ発電が火力上回る - 太陽光は10年で30倍増https://t.co/fsLhbmBuKm
— 共同通信公式 (@kyodo_official) September 20, 2025
中国では太陽光発電がどれくらい普及しているのか
中国は世界最大の太陽光発電大国です。2023年時点での太陽光発電の設備容量は日本の5倍以上と言われており、特に内モンゴル・青海省・甘粛省などの砂漠地帯を活用して巨大なメガソーラー群を建設しています。
- 特徴①:森林を切らずに、不毛地帯に設置している
- 特徴②:送電インフラを国家主導で整備している
- 特徴③:発電能力が余りすぎて、現地では電気が余っている地域もある
一方で、中国国内でも「景観破壊」や「パネル廃棄物問題」が深刻化しており、10〜20年後には大量の産業廃棄物処理が社会問題化すると予想されています。
日本は森林を切って太陽光を設置しているケースが多く、中国とは「土地の使い方」の前提が異なることを理解する必要があります。
北海道・釧路のメガソーラー問題
北海道・釧路地域では、釧路湿原周辺や丘陵地帯で大規模なメガソーラー計画が進められてきました。世界的な自然遺産に隣接するエリアということもあり、「景観や生態系への影響が大きすぎる」として住民や専門家、またSNS上でも反対の声が上がっていました。
現在のところ、建設が完全に中止されたわけではありません。しかし、
- 遺跡の届出漏れなどの法令違反が発覚
- 国(文化庁)が調査に介入
- 地元自治体が“太陽光発電の許可制条例”の導入を検討
といった事態を受け、事業者は当初の計画どおりには進められなくなっており、事業の進め方そのものの見直しを迫られている状況です。
また、北海道特有の環境リスクも依然として指摘されています。
- 冬季の積雪によって発電効率が大幅に低下
- 春先の融雪水による土砂災害の可能性
- 湿地帯の造成による地下水の流れの変化と生態系への影響
さらに観光関係者からは、「釧路湿原の大自然のパノラマが、銀色のパネル群に置き換わるのは耐えられない」という声も上がっており、単なるエネルギー政策の問題ではなく、地域の景観・文化・観光資源の存続に関わる問題として捉えられています。

鴨川・釧路に共通する問題は「行政指導だけで止まらない」こと
自治体が住民説明を求めても、事業者が「法的拘束力がない」と言えば工事が進んでしまいます。現状では行政指導には強制力がなく、止められない構造になっています。
再エネは必要だが「やり方を間違えれば逆効果」
太陽光発電そのものが悪いわけではありません。しかし、
- 森林や湿地を破壊してまで設置するべきか
- 所有者が不明確なまま工事を進めてよいのか
- 撤去や災害時の責任は誰が負うのか
といった根本的な問題が解決されない限り、「再生可能エネルギーのはずが環境破壊になる」という矛盾が続いてしまいます。
エネルギー政策は「量」ではなく「質」が問われる段階に入っているのではないでしょうか。