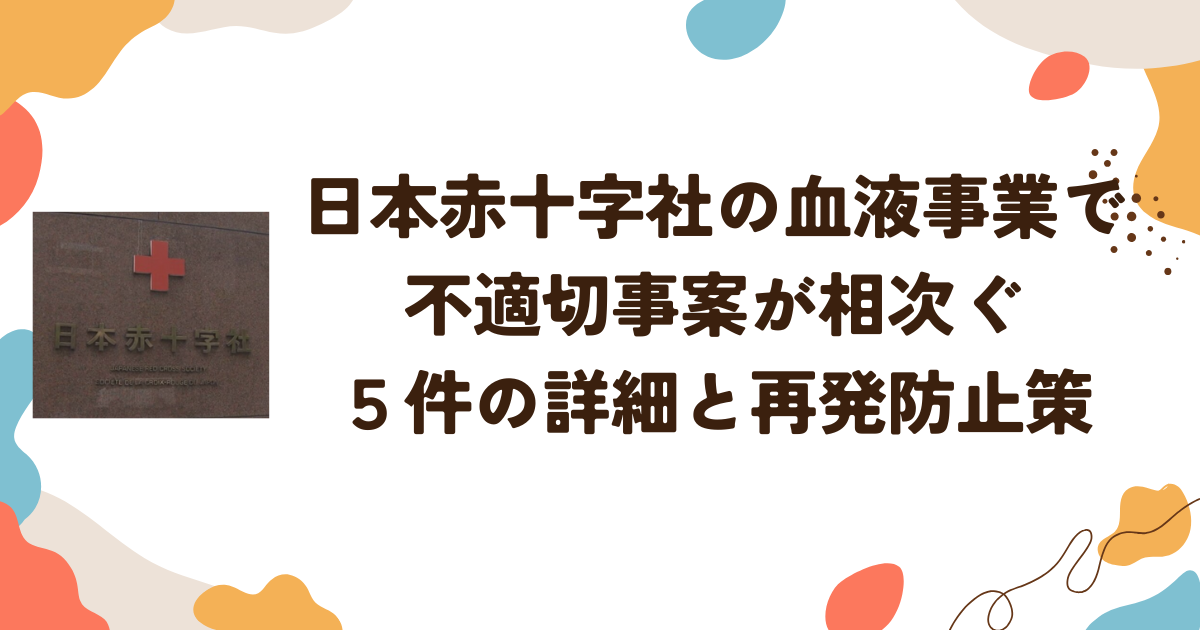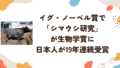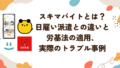日本赤十字社は、献血をはじめ、医療・救護・国際人道援助など多岐にわたる活動を行う日本の公益組織です。献血者の善意で成り立つ血液事業は生命線ともいえ、その安全性と適切な管理は極めて重要です。
ところが、今年(2025年)5月以降、血液製剤の管理や献血の現場で不適切な取り扱いが5件相次いでいることが明らかになり、社会の関心を集めています。
本記事では、その内容、背景、過去の類似例、そして今後どうすべきかについて整理します。
日本赤十字社とは何か
まず、日本赤十字社について簡単におさらいします。
- 日本赤十字社は、1877年(明治10年)創立の公益法人で、日本における赤十字運動を担う組織です。日本赤十字社法に基づいて設立され、災害救護、医療・病院事業、看護師養成、国際協力、血液事業(献血・血液製剤の製造・輸送・供給など)などを主な事業としています。
- 組織は全国に都道府県支部があり、多くの赤十字病院・献血ルーム・血液センターを運営しています。
- 献血・血液製剤事業は、国が求める輸血用血液製剤の安全性・供給の確保という観点から、日本ではほぼ唯一の採血事業者および輸血用血液製剤の製造販売事業者としての役割を負っています。
そのため、日本赤十字社の血液事業に問題が起こると、患者や医療機関だけでなく、献血者・国民全体に対する信頼が問われる事態になります。
日本赤十字社の不適切取り扱い5件の概要
2025年5月から9月にかけて、日本赤十字社の血液事業において、以下のような5件の不適切・事故事案が報告されました。内容は公式発表と報道等に基づきます。
| 時期 | 内容 | 規模・影響 | 原因・備考 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 東京都の血液センターで冷凍庫の電源が落ちるトラブル。新鮮凍結血漿(FFP)約 1万3,700本 が輸血用として使用できなくなる。 | このうち、品質には問題がなかったため、転用可能な原料血漿として扱う。医療現場への納品には影響なし。 | 冷凍庫更新時に機器の付け間違いがあり、それに伴う電源遮断。設備の制御盤や端子台などの設置に誤りがあったこと。 |
| 9月(複数) | 北海道・移動献血会場で、献血者A(女性)の採血後、採血針をそのままにして次の献血者B(男性)に使用してしまう。使用済みの針が再使用されるという非常に重大な誤り。 | 健康被害は確認されていないとのこと。 | 操作ミスおよび手順確認の不足。 |
| 9月 | 福岡県で、献血者33人分の血液製剤を搬送する際、保冷剤が規定数未満だったため温度管理基準を逸脱し、33単位を廃棄処分。 | 廃棄による損失および献血者への説明責任。患者への供給への影響は報道時点では限定的とのこと。 | 最終確認の手順を怠ったこと。保冷材の数を確認する工程が守られていなかった。 |
| その他数件 | 記者会見で「5件相次いだ」とされており、上記の他にも細かな処理ミスや手順違反が含まれている。 | 総じて、輸血用血液製剤の安全性・管理体制に対する信頼を損なう事案。献血者・医療機関双方に対して不安が広がっている。 | 報告・公表の遅れも指摘されている。発生から厚生労働省への報告、公表までに時間がかかったケースがあった。 |
日本赤十字社はこれらを重く受け止めており、以下のような対応を発表しています。
- 全国の血液センターでの一斉点検:手順・規則がきちんと守られているか確認をする。
- 安全管理室を新設:血液事業における安全管理体制を強化する目的。
- 報告・公表のあり方見直し:発生から公表までに時間がかかったことを受け、情報公開・報告の迅速化を図る

これらの事案の問題点
上記のような事案には、以下のような問題点があります。
- 献血者の善意の裏切り
献血は多くの場合、見返りを求めず、他人のために自らの血を提供する行為です。これを適切に管理できなければ、献血離れ・信頼の低下を招くおそれがあります。 - 安全性・品質保証の失墜
血液製剤は温度管理が厳しく定められています。冷凍庫の電源トラブルや保冷剤不足は、製剤の品質を損なうリスクがあります。 - 手順・管理体制の甘さ
使用済み針の誤使用、搬送時の保冷剤数の確認漏れなどは、「誰が」「いつ」「どのように」業務を行うかという手順・確認体制の欠如を示しています。 - 報告・公表の遅れ
問題が発覚してから厚生労働省への報告や公表までにタイムラグがある事例があり、透明性・説明責任の観点で批判されています。
日本赤十字社の過去の不祥事・類似事例
これらの新しい事案に先立って、日本赤十字社にはいくつかの過去の不祥事や医療事故が存在します。以下、把握できる主なものを紹介します。
| 事例 | 内容 | 発生年・概要 |
|---|---|---|
| 新鮮凍結血漿(FFP)の保管温度逸脱 | 昨年(2024年または2025年初期)、東京都赤十字血液センター辰巳供給出張所で、設備更新時の制御装置の端子台不適合が原因で冷凍庫の温度が基準を超えて停止。対象製剤13,748本を輸血用に使用できず、原料血漿への転用を決定。 | 医療現場への供給には影響なかったが、製剤の用途変更などの対応が必要となった。 |
| 医療過誤:誤った患者への輸血 | 過去に、輸血製剤を患者と照合せず誤った患者に輸血してしまった事例が報告されている。たとえば、製剤のバーコード照合をせず、患者のリストバンドとの照合も不十分であったケース等。 | 医療安全情報として公開され、各医療機関でマニュアルの見直し・バーコード等認証システムの導入・確認手順の強化がなされてきた。 |
| 京都第一赤十字病院での医療安全管理の問題 | 最近(2023〜2024年)京都第一赤十字病院の脳神経外科等で、安全管理・説明責任・記録管理などに不備があるとして、行政指導を受け、専門医研修施設認定が一時停止された。 | 病院としての組織的な安全文化の欠如が指摘されており、外部評価委員や学会等からの指摘を受け改善を求められている。 |
これらの例からも、一部はすでに制度的な対応(マニュアル整備・認証システム導入・外部監査・公表制度)を通じて一定の改善が図られてきました。しかし、今回の5件のような“複数の事案が短期間に連続”する形は、組織全体の管理体制・安全文化の見直しを強く促すものです。

なぜ今回、こうしたミスが相次いだのか(背景と思われる要因)
報道・日本赤十字社の発表内容からうかがえる、原因や背景には以下のような点が挙げられます。
- 設備・機器の設置・更新時のミス
冷凍庫の制御盤・端子台の誤った設置、電源の遮断など、機械・電気関連の工事や更新時のチェックが不十分だったことが原因として挙げられています。 - 手順・標準操作 の遵守不足
保冷剤の数を確認する最終チェックを怠った、針の使用後処理・使い回し防止の手順が守られていなかった、などの手順漏れが見受けられます。 - 人的ミス・意識の問題
多忙な現場では、確認作業が省略されたり、習慣として手順を確認しないまま移行してしまうことがあります。また、予備・代替策の把握が不十分であった可能性があります。 - 報告・公表の仕組みの遅さ・不備
発生後の対応では、「発生から公表までの時間が長い」ケースがあることが指摘されており、情報を速やかに共有する体制が弱かったことが、信頼低下を助長しています。 - 組織の安全管理体制の強化不足
複数の施設・拠点で類似のミスが起きていることから、個別の現場対策だけでなく、横断的・包括的な安全管理監査、教育、仕組みづくりが未だ徹底されていなかった可能性があります。
まとめ:信頼回復への道筋
今回の5件の事案は、命に直結する血液事業という性格上、日本赤十字社にとって重い問題です。ただ、これを契機として体制を見直し、安全文化を根付かせ、公開性を確保できれば、将来的には信頼を維持・回復できる可能性があります。
国民としても、献血という形での協力をする上で、「どのような管理がなされているか」「問題があったときにどう対応されるか」を知る権利があります。報道・公表の透明性は、組織にとって面倒であっても、信頼を維持する基盤です。
私たちは、血液を提供する側・受け取る側双方の視点から、この問題を注視し、より安全で誠実な血液事業が実現されることを願ってやみません。