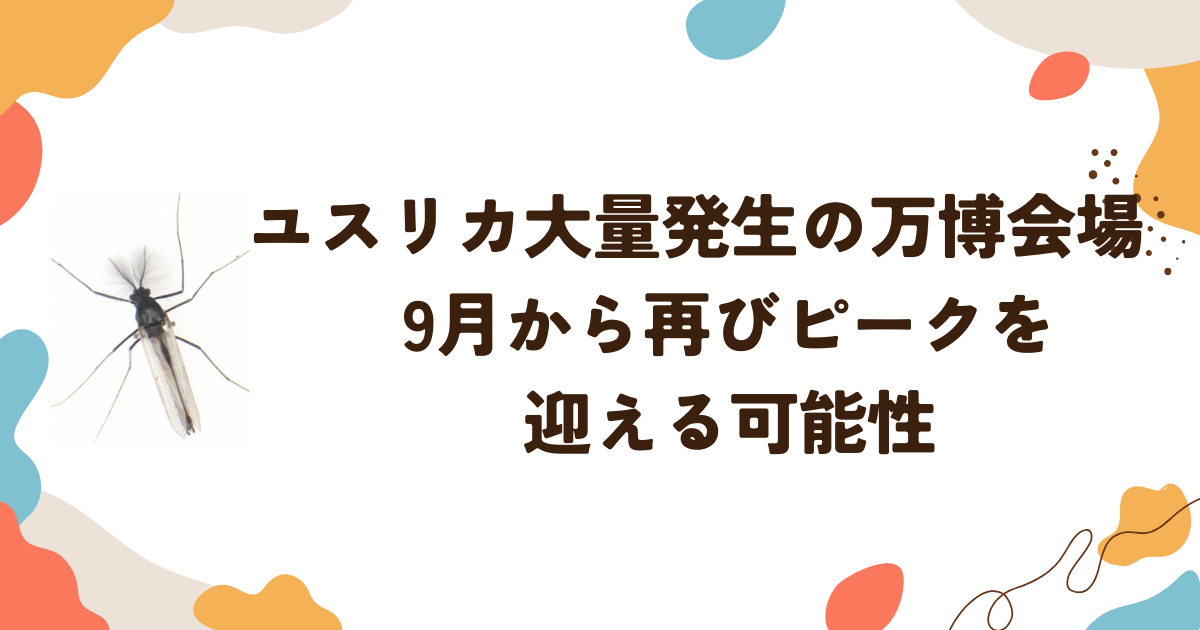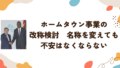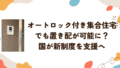今年5月、大阪・関西万博の会場である夢洲(ゆめしま)で「ユスリカ」が大量に発生し、来場者から「蚊のような虫が群がっていて不快」「服や髪にまとわりつく」といった声が相次ぎました。万博協会は会期末の9月下旬から10月中旬にかけても再び大量発生が予想されるとし、対応策を公表しています。しかし、薬剤散布は行わず、物理的な侵入防止などで対策する方針です。
本記事では、前回の発生経緯を振り返りながら、ユスリカの生態や大量発生の背景、そして対策の現状について詳しく解説します。来場予定の方にとっても知っておきたい重要な情報です。
ユスリカとはどんな虫か?
ユスリカはハエ目ユスリカ科に属する昆虫でハエの仲間です。見た目が「蚊」に似ていますが、人を刺したり血を吸ったりすることはありません。成虫の口は退化しており餌を摂らず、主に水辺で羽化後、数日から1週間ほどで寿命を迎えます。
幼虫は水中で生活し、泥や有機物を餌に成長します。湖沼や河川、人工の水辺に発生しますが、万博で大量発生したユスリカは淡水と海水が混じり合う汽水域に生息する「シオユスリカ」。淡水でも繁殖することができます。
成虫は夕方から夜にかけて「蚊柱」と呼ばれる群飛を行い、光や風の条件によって特定の場所に集まります。この習性のため、大規模イベントの会場などで発生すると、人の目に触れやすく、一気に問題が顕在化します。
ユスリカ自体は人を刺したり吸血しませんが、大量発生すると衣服や顔に付着するなど強い不快感を与えるほか、死骸が建物や設備に堆積して衛生管理上の課題を引き起こすことがあります。また、大量に発生した際の死骸がアレルギーの原因となることがあります。
万博会場でのユスリカ大量発生(5月)の経緯
5月、夢洲の会場ではユスリカが大群となって飛び交い、特に夜間は大屋根リングや各パビリオン付近に群がりました。SNS上には、無数の小さな虫がライトに集まり、壁や床を覆う様子、展示物に付着する様子が投稿され、瞬く間に拡散しました。
発生源は会場内の「つながりの海」や「ウォータープラザ」と呼ばれる人工の水辺であるとされています。これらの水域は浅瀬で流れが少なく、魚などの天敵がいないため、ユスリカの幼虫が大量に育つ環境が整っていました。
運営側は発生後、緊急に調査を行い、入口にビニールカーテンを設置するなどの対応を開始しましたが、薬剤の散布は行われず、根本的な抑制は難しいまま問題が注目されました。

なぜ再び9月〜10月にユスリカが大量発生するのか?
ユスリカは気温の変化に合わせて発生数が増減します。夏の猛暑時には数が減少しますが、気温が下がり、昼夜の温度差が大きくなる秋は再び羽化が活発化します。
専門家によると、ユスリカの発生ピークは9月下旬から10月中旬に訪れることが多く、会期末の万博会場でも同様の現象が起きる可能性が高いと予測されています。
秋は水辺の栄養状態も変化します。夏に蓄積した有機物や藻類が分解される過程で、幼虫にとって豊富な餌環境が整い、一斉に成虫が羽化する条件がそろうのです。
ユスリカ大量発生に結びつく要因
ユスリカの大量発生は単一の原因ではなく、複数の環境要因が重なった結果と考えられます。夢洲のケースでは次のような要因が指摘されています。
鳥類の減少による生態系バランスの崩壊
夢洲は造成前、シオユスリカを含む多様なユスリカ類が生息し、それを餌とするシギ・チドリ類などの渡り鳥や、ヨシ原にすむ鳥類が生態系を支えていました。ところが万博会場の建設により浅瀬やヨシ原が消失し、鳥類の生息環境が失われました。
天敵である鳥が減ったことで、ユスリカが異常繁殖する土壌ができあがったと考えられます。
水質悪化と人工水域の存在
会場内の水辺は、魚や水生昆虫といったユスリカ幼虫の捕食者が少なく、水質も富栄養化しやすい環境です。このため、ユスリカにとって絶好の繁殖場所となりました。
高温環境
気温が高いほどユスリカの発育速度は速まり、短期間で世代交代を繰り返します。5月の発生は春から初夏にかけての気温上昇が後押ししたと見られます。
照明やライトアップ
成虫のユスリカは光に集まる性質があり、会場の大規模な照明や演出によって一か所に誘引されました。その結果、来場者が一度に大量のユスリカを目にする事態が発生したのです。
これらの要因が複合的に作用し、「万博会場特有の大発生」につながったとされています。
大阪・関西万博の会場でユスリカが大量に発生している状況は、当初から現在も続いていますが、その状況は時期や場所、そして対策によって変化しています。
当初の状況と現在の状況
- 当初(5月~6月頃): ユスリカの発生が特に顕著だった時期で、SNSなどでは大屋根リングの壁や床、彫刻、看板などに大量のユスリカが付着している画像が広く拡散されました。特に、水辺に近いエリアや夜間に照明が灯る場所では、大群が飛来する様子が目撃されていました。
- 現在の状況(9月時点): 依然としてユスリカの飛来は確認されていますが、時期や時間帯によって変動があります。ユスリカは猛暑が苦手なため、夏のピーク時には出現が落ち着く傾向が見られました。しかし、涼しくなる9月下旬から10月中旬にかけて、再び大量発生のピークを迎える可能性が指摘されています。
対策と課題
万博協会は、ユスリカの大量発生を受けて対策本部を立ち上げ、様々な対策を講じています。
- 発生源の特定と清掃: ユスリカの幼虫が発生しやすいウォータープラザや「つながりの海」周辺の清掃や環境改善が行われています。
- 忌避剤・殺虫剤の散布: 来場者がいない夜間に、大屋根リングの植栽帯など、特定の場所に忌避剤や殺虫剤が散布されています。
- 屋内への侵入対策: パビリオンなどの屋内施設では、ユスリカの侵入を防ぐために、ドアや窓の隙間に防虫ブラシやネットを取り付けるなどの措置が取られています。
- 照明の工夫: ユスリカは光に集まる習性があるため、夜間のライトアップ方法や照明の種類を工夫することで、ユスリカの飛来を抑制する試みも行われています。
万博協会の対応と薬剤を使わない理由
博覧会協会は、ユスリカの発生源である「つながりの海」などへの薬剤散布を行わない方針を明言しています。その理由は以下の通りです。
- 発生源が広範囲にわたり、薬剤を撒いても効果が限定的である
- 会場のテーマである「環境共生」「持続可能性」に配慮し、生物多様性を守る姿勢を示す必要がある
- 薬剤散布は魚や他の昆虫にも影響を及ぼし、生態系に悪影響を与える恐れがある
その代わりに、施設入口にビニールカーテンを設置する、来場者への情報発信を強化するなど、物理的な侵入防止策をとっています。大量発生が確認された場合には公式サイトなどで発生エリアを公開し、来場者が事前に把握できるようにする予定です。
来場者ができる対策
運営側の対応に加え、来場者自身が工夫できる点もあります。
- 夕方から夜の屋外滞在を控える:ユスリカの活動が活発になる時間帯を避ける
- 長袖・長ズボンを着用:肌の露出を減らし、付着による不快感を軽減する
- 明るい色の服装を選ぶ:黒や紺といった暗い色に集まりやすい習性があるため
- 防虫スプレーを活用する:完全ではありませんが顔や体周りへの飛来を減らす効果があります
- 多く発生する時間帯や場所を避ける:日中の時間帯に行く、ライトアップされた場所を避ける
- 会場内の公式情報をこまめにチェック:発生エリアの情報が公開されるため、移動や滞在の参考にできます
まとめ
ユスリカは人を刺すことはなく、直接的な健康被害を及ぼすわけではありません。しかし、会場での大量発生は強い不快感を与え、イベント運営に影響を及ぼしかねません。
夢洲では、会場造成に伴う生態系の変化で鳥類が減少し、水辺環境の悪化も重なって、ユスリカが増えやすい条件が整いました。さらに秋の気候が重なることで、9月末から10月中旬にかけて再び発生のピークを迎える可能性が高まっています。
万博協会は薬剤散布を行わず、生物多様性に配慮した対策を選択しました。来場者にとっては不快な思いをする場面もあるかもしれませんが、事前の知識と工夫によって快適さを保つことは可能です。
大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げています。その理念の裏には、人間と自然の共存をどう実現するかという課題が存在します。ユスリカ問題はその象徴的な一例といえるでしょう。